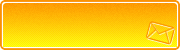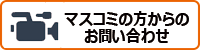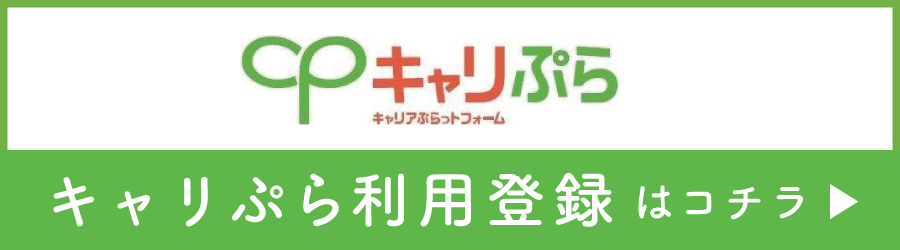- ホーム
- べあーずBlog略して【べあぶろ】 「就活」「仕事」「人生」のOS
- 就活で考え行動し失敗して成長する
就活で考え行動し失敗して成長する
2015/11/27
こんにちは。べあぶろ中の人です。
今日の記事は2年半前のものですが、「キャリぷらが目指すもの」についてすごく分かりやすく書かれています。
相手によって教え方を変えたり、全てを教えるのではなくヒントを出して自分で考える力を身につける機会をつくる、「考えて」「行動して」「失敗して」「学んで」「成長して」いく力を教えてくれる場所はなかなかないと思います。
キャリぷらに来るだけであなたの人生が変わるかもしれませんよ(^○^)
2013.4.8たなべあーFB投稿記事
キャリぷらが目指すもの。
それは2年前作った当初から明確で、
「学生にとって役立つ支援を、とことん本気で提供していくこと」だ。
そして、そのことが全てにおいて優先されることが、なによりも重要だと考えている。
あとは、
役立つ支援が相対的にどれだけ的を得ているか、時代のニーズに合っているかに尽きるだろう。
選ばれるか淘汰されるかは、そこが分かれ目になるのだろうと考えている。
そういう意味で、「役立つ支援」に関して、私の考え方はこうだ。
子どもが初めてコマなしで自転車に乗る、としよう。
「よし、じゃあ後ろを持っててあげるから走ってみようね。」と言って、知らぬ間に手を離すという方法が定番だが、それがいいという子にはそうする。
誰かが乗っているのを観察しながら、コツをつかんで乗れるようになりたい、という子にはそうさせる。
とにかくひとりで乗りまくって、何度も何度も転んで怪我だらけになりながら乗れるようになりたい、という子にはそうさせる。
同じ立場の子ども同志で、教え合って、励まし合って乗れるようになりたい、という子にはそうさせる。
どうやって乗れるようになったのか、そのときのことを教えて欲しいと言ってくる子には、自分の話や見聞きした話を教えて聞かせる。
要は、上手くいく方法はこうだ、やり方はこうだと決めてやらない。
それによって学生が、「自分で考える」ことや「自分の行動を通じて学ぶ」機会を奪わない。
その機会が、最も人を強くするし、賢くすると私は思っているからだ。
だから、学生は「考え」「行動する」ようになる。
さらには、「場」と「時間」を共有しているから、他者が見えることで自分が見える。
ときには他者に学び、真似をしてみて、自分を成長させることにも繋がる。
結局、目の前にある現実、起きてくる出来事、取り組むべき課題に対して、「考えて」「行動して」「失敗して」「学んで」「成長して」いく力を、本人が経験を通じて身につけることが一番で、それこそが社会に出て生きていくうえで、会社に入って仕事をしていくうえで、最も再現性のある力になると私は考えている。
であれば、だ。
最適な就職支援は、最適な採用支援と必ず繋がるはずである。
それを一言で表したのが、
「すべては学生と日本の未来のために」という我が社の企業理念である。
だからキャリぷらは、これからもとことん本気でそういった「場」を作っていく。
「持続可能な仕組み」や「サービス」を提供していくことで、この理念を具現化していきたい。

よかったらいいね!やリツイートをよろしくお願いします(^^)vBy中の人